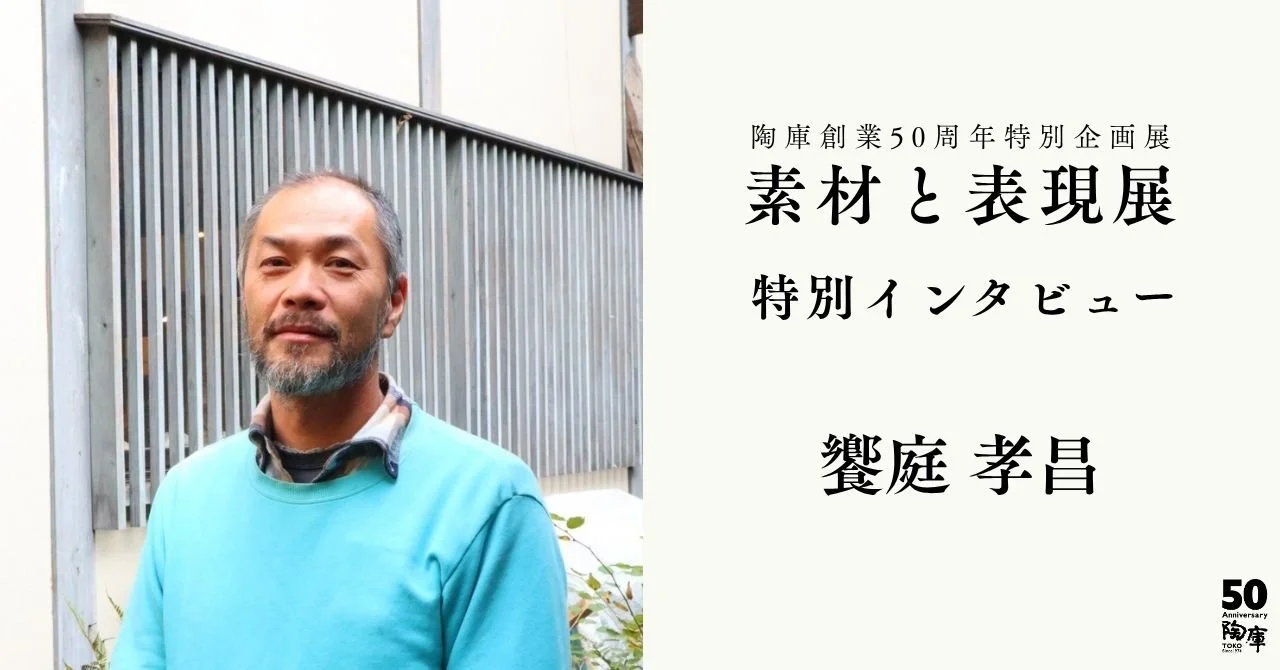作家インタビュー「饗庭孝昌|作ることは、生きること。芯棒ろくろと寺山の土」
陶庫創業50周年特別企画展「素材と表現展」の開催に伴い、作家さんの特別インタビュー企画を開催。
作家の作陶に対する想いに迫ります。
饗庭孝昌|作ることは、生きること。芯棒ろくろと寺山の土
芯棒ろくろのわずかな“揺れ”が形を決め、寺山の土が色を導く。
効率や安定を求めず、素材の声と向き合いながら「生き方そのものを作品にする」と語る饗庭孝昌さん。
古信楽の壷や江戸の泥絵、庶民の手仕事に宿る“人生の美”を手がかりに、土の質感と人の営みを重ね合わせるように制作を続けています。
今回の「素材展」では、自然の力と人の呼吸が響き合う造形を通して、「技術」と「哲学」のあわいにある陶芸の原点を問いかけます。。
TAKAYOSHI AEBA
饗庭 孝昌
略歴
1969年:東京都に生れる
1993年:高内秀剛氏に師事
1998年:栃木県益子町にて独立築窯
2013年:登り窯築窯
庶民の暮らしにある「人生の美」
陶庫── この鏡絵はどこか懐かしい雰囲気がありますね。
饗庭さん── 観光地のおみやげなんですよ。木崎湖の風景画です。工芸的な絵で泥絵のような雰囲気があったので買いました。縦長の小さいベニヤに貼り付けて、板の下半分に小さい鏡がはりつけてある安っぽいつくりです。
陶庫── 泥絵、ですか。
饗庭さん── そう。江戸の泥絵というのは、民芸の世界ではよく知られているジャンルなんです。昭和30〜40年代くらいまでは、そういう工芸的な絵を生業にしていた老絵師が生き残っていたんじゃないかな。僕はそういう“人間の流れ”に惹かれるんです。
陶庫── “人間の流れ”というのは?
饗庭さん── ものづくりって、技術の話だけじゃなくて、その背景にある人生の積み重ねだと思うんです。たとえばこの泥絵にも、名もない人が一生懸命生きた時間が刻まれている。そこに美しさを感じます。理想だけが美じゃなくて、なんでもない日常の中にも“人生の美”はある。柳宗悦が李朝の器に見たものと、近い感覚かもしれません。
陶庫── 値段がつかないようなものにも、そういう魅力がある。
饗庭さん── ええ。明治の版画でも、ボロボロで額も割れていて、数百円で売られているようなものに、僕は惹かれます。値段じゃないんです。むしろそういう中に、誰かが生きた証のような輝きがある。
饗庭さんの作品
「浜田庄司がやったこと」 生き方を作品にする
陶庫── 饗庭さんはよく「生き方そのものが作品」と話されます。
饗庭さん── 器を作るだけが仕事じゃないんです。山を整えたり、田んぼをやったり、手漉きの粘土を作ったり。そうした生活のすべてが作品につながっていると思っています。暮らしを通して自分がどう生きたかを示すこと、それが僕にとっての表現なんです。
饗庭さん── 浜田庄司は、その生き方をまさに体現した人です。ウィリアム・モリスや柳宗悦の思想を受け継ぎながらも、自分の信じる「濱田の芸術」をつくった。壺や茶碗を一つ見ても完成度が高く、同時に理念をもった運動としても強かった。単なる個人の表現ではなく、地域と社会を巻き込む力があったんです。
陶庫── 作ることが社会とつながっていたんですね。
饗庭さん── そうです。浜田さんが益子に根を張ったのも、ただの移住じゃない。あの時代に東京を離れ、土地とともに生きる道を選んだ。結果的に、それが多くの人の生き方に影響を与えた。僕も、器づくりの延長線上にそういう生き方を見たいと思っています。
饗庭さんの自宅
揺れのある形|芯棒ろくろを使う理由
陶庫── 轆轤(ろくろ)の話を聞かせてください。今はベアリング付きが主流だと聞きますが。
饗庭さん── 僕は芯棒の轆轤を使っています。ベアリングの轆轤は回転が安定していてブレない。でも芯棒ろくろは中心を取るのが難しくて、常にわずかに揺れる。その揺れが、形の生命感になるんです。
饗庭さん── **僕の轆轤は、小瀧悦郎さんという故人の工房から譲ってもらったものです。ベアリング轆轤ではないブレがあって、それと自分の呼吸、外界に対して反応する自分の生命エネルギーの発し方みたいなもので固有の形ができるんです。**欅でできていて、長年仕事に使われたから表面が削れてボロボロ。でもそれがいい。新品のベアリング轆轤では出ない“動き”があるんです。薪窯をいくら丁寧に焚いても、轆轤が安定しすぎていたら、表情が死ぬこともあると思う。
饗庭さんの芯棒ろくろ
陶庫── 効率とは逆の方向にある道具ですね。
饗庭さん── ええ。パワーがないから大きいものは作れません。でも、継いだり、紐作りを組み合わせたりすればいい。信楽の人たちも下部は轆轤、上は紐作りというやり方をしています。完璧に芯を合わせないからこそ、微妙な“ずれ”が積み重なって味わいになる。あのずれは偶然ではなく、意図的に受け入れているんです。
陶庫── 古いものを研究して、自分の作品と何が違うのかを探るという話も印象的です。
饗庭さん── 僕はコピーを作ろうとは思っていません。でも、古いものがなぜ魅力的なのかを考え始めると、どうしても一つずつ突き詰めたくなる。土の質、轆轤の回転、焼きの温度――そういう要素を一個ずつ解いていくと、「ああ、これじゃなきゃだめなんだ」と納得する瞬間がある。当たり前だと思っていた技術を言葉で整理することで、初めて見えることもあります。
饗庭さん──制御された電気窯や精製された粘土で作るのとは、根本的に別の世界です。芸術家として、人がやっていないことをやる――それが僕の中での芸術の定義に近いですね。
饗庭さんの芯棒ろくろ
寺山と灰釉──素材が導く色
陶庫── 寺山の原料についても詳しく聞かせてください。
饗庭さん── 寺山の土は白くて少し粘りがあります。掘りたてだと硫黄の匂いもします。耐火度が高く火に強いんですが、その分、溶けにくい。だから灰の量や種類を調整して溶かしていくんです。青磁というのは白っぽい石に灰を混ぜて焼くことで生まれます。鉄分が完全に抜けた土はほとんど存在しないから、少し鉄が残ることで緑がかる。天草の陶石だと青寄りに、寺山だとややグリーン寄りに発色します。
陶庫── 灰釉の調合はどうしていますか。
饗庭さん── まず灰だけで試して、なめらかさがほしいときは長石や粘土分を少し足します。灰だけだとまだらになるので、そこに“粘り”を持たせる感じです。溶け方は材料同士の反応で変わるので、灰を多く入れれば溶けるというものでもない。材料同士のバランスを見ながら調整するのが大事です。なるべくシンプルに始めて、経験で少しずつ加えていくのが僕のやり方です。
寺山の土
「素材を拾う」という仕事
陶庫── 素材を探すという行為にも、哲学を感じます。
饗庭さん── 若いころ、窯作りや修理であちこちの工房を訪ね歩いたんです。そのときに、みんな違うことを言うんですよ。それが面白くてね。素材は工事現場や林道の造成中に出てくることもあります。現場の人にお願いして、少し分けてもらったり。そうやって試しているうちに、もうその現場がなくなってしまうことも多い。だから、地域の中で原土の確保をして、希望する人が使える仕組みがあればいいなと思います。
陶庫── 個人の探究にとどまらない視点ですね。
饗庭さん── そう。自分ひとりの制作も大事ですが、地域全体で素材をどう残すかも同じくらい重要です。誰かが得をするんじゃなくて、みんなで守るという意識がないと、益子の素材文化は続かないと思います。
古い焼物の陶片
風景とともにある作品
陶庫── 赤い壺が印象的でした。
饗庭さん── 細長い形のやつですね。あれは土を紐作りで足しています。大津沢という地区で採れた土で、焼きあがりが古信楽の壷に似ていると以前から思っていたのですが、登り窯の一番の部屋なら火が直接当たるので古信楽みたいになるかと思って焼いてみました。信楽よりは少しくすんだ色だけど、綺麗な緋色が出たと思います。壁際は灰が多く乗って、中央はさらっとしている。裏と表で全く違う表情が出て、そこが面白い。自然の力に任せるしかないんです。
生き方としての陶芸
陶庫── 改めて伺います。「生き方が作品」という言葉の意味を、もう一度教えてください。
饗庭さん── ものを作るのは自分の努力でできます。でも、まわりを変えるには、人との関係や社会との関わりを考えなければならない。言葉で「こうあるべき」と言うだけでなく、自分の暮らしや作品を通してそれを示すこと。それを感じ取ってくれる人がいれば、それがいちばんの伝わり方だと思います。
饗庭さん── 僕の作品を好きだと言ってくれる人は、たぶんどこかで今の工芸に違和感を持っているんでしょうね。「もっと素朴で、もっと真っ直ぐでいいんじゃないか」と思っている。そういう人たちと、ゆるやかに響き合っていけたら嬉しいです。