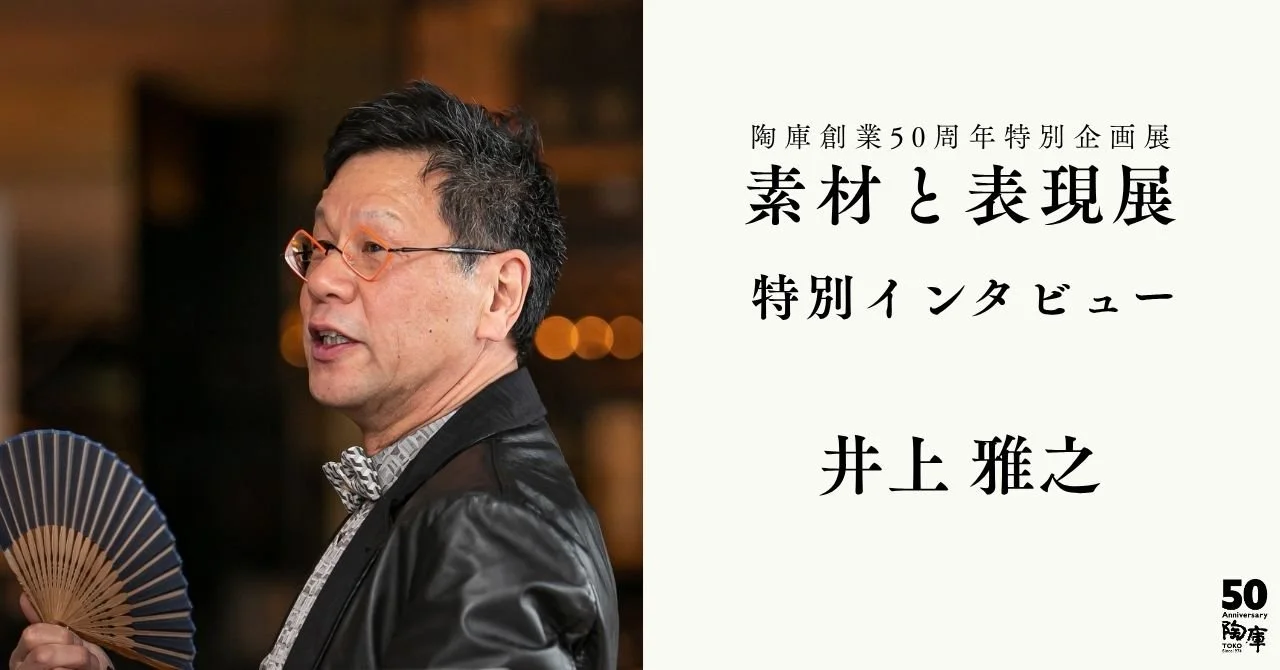作家インタビュー「井上雅之|受け取って、もう一度外に出す。」
陶庫創業50周年特別企画展「素材と表現展」の開催に伴い、作家さんの特別インタビュー企画を開催。
作家の作陶に対する想いに迫ります。
井上雅之|受け取って、もう一度外に出す。
多摩美術大学での教授を終え、制作に専心する井上雅之さん。
学生時代に偶然出会った“焼き物”はいまも彼の出発点であり続ける。
土という素材と向き合い、受け取った感覚をもう一度外に出す往還。その回路こそ、自己表出と指示表出を結ぶ表現だと井上さんは語る。陶庫スタッフとの対話から、その現在地をたどっていく。
MASAYUKI INOUE
井上雅之
略歴
1957年:神戸市に生まれる
1983年:多摩美術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
1985年:多摩美術大学大学院美術研究科修士課程修了
多摩美術大学美術学部絵画科油画研究室副手~1987年
1987年:同研究室助手~1989年
1991年:多摩美術大学美術学部絵画科油画専攻非常勤講師~1998年
1998年:多摩美術大学美術学部工芸学科助教授~2006年
2006年:多摩美術大学美術学部工芸学科教授~2023年
出会い──「手のなかで形が立ち上がる」
陶庫──
まずは、焼き物との出会いからお聞かせください。
井上さん──
最初はまったく興味がなかったんですよ。美大に入ったのも「なんとなく美術をやってみたい」くらいで。中学生のころから漠然と憧れていただけで、明確な目的もないまま多摩美術大学の油絵科に入りました。
でも、なんとなくやっていたから二年生くらいでつまらなくなってきて(笑)。大学って、入っただけじゃ何も起きない。自分で探さないと始まらないんですよね。
そんなとき、油絵や版画のほかに陶芸の講座があって、何となくろくろに触ってみたら、手を動かすうちに形が立ち上がってきた。「あ、これは面白いな」と。
白いキャンバスの前では、自分が“描きたい”と思わない限り何も起きなかったのに、土を触ると“起きてしまう”。その瞬間、何かが自分の中で動いたんです。
当時の僕には、とにかく「面白かった」。でも何が面白いのかはわからない。どうしてもろくろをやっていたいから「茶碗作ってます」と言っていた。
「茶碗作ってます」と言えば誰も何故とは聞いてこない。でも感じた“面白さ”の正体はうまく言葉にできないから自分でも楽。だから、ろくろでできることを“仮の形”としてやっていた。器として使うこともなく、ただ作る。何をしていいかわからないまま、壺や皿を作る。そんな一年がありました。
「目の前にあるもの」への反応
井上さん──
絵の話に戻ると、学生当時はモデルを描いたり、静物画を描いたりするのが好きでした。最近わかったのは、僕は“目の前にあるものには反応できる”ということ。何もないところから描けと言われると、もう折れる(笑)。自分の頭の中には何もない、とわかっているから。
でも「これを描こう」と対象があれば描ける。面白そうだからやってみよう、という気持ちにもなる。たぶん、目の前にろくろでできた形があったから続けられたんだと思います。
学生にも言ってました。「僕らの頭の中には何もない。だからまず受け取ったものを外に出す」。作品でも文章でも、とにかく外に出す。外に出した瞬間、はじめて自分の目でも“見える”。自分の作ったものも、外に置かれれば“対象”になります。
モチーフは対象ではなく動機
井上さん──
「何をモチーフにしているんですか」と聞かれるのが一番苦手です。(笑)たとえば夕日を見て「きれいだな」と思ったとき、描くのは“夕日そのもの”ではない。そのとき自分が受け取った何か、なんです。
写真を撮るのも方法のひとつ。でも撮っただけだと、自分が感じたものとの差がある。だから編集したり、加工したり、詩や音楽に置き換えたりもする。十人いれば十通り。
モチベーションとモチーフは本当は同じ。どちらも“動機”です。夕日は再現できない。だから別の形で“再表出”する。それが表現だと思います。
表現とは、受け取って再び出すこと
井上さん──
表現は日本語だと一言ですが、英語では二つに分かれます。エクスプレッション(expression)とリプレゼンテーション(representation)。
エクスプレッションは“吐き出す”ことで、リプレゼンテーションは“受け取ったものをもう一度外に出す”こと。僕は後者を大切にしています。
たとえば「夕日がきれいだ」と感じた出来事を、別の形にしてもう一度外に出す。SNSでの吐露とは違い、共有可能に整える行為。それを表現だと考えています。
焼き物のプロセスと非可逆性
陶庫──
造形的な仕事はいつから始められたのですか?
井上さん──
大学院のころ、磁器で器を作っていてヒビや割れで失敗作が山ほど溜まりました。ある日ふと、その欠片を見て「これ、きれいじゃん」と思った。毎日見ていた“ダメなもの”が急に美しく見えたんです。変わったのは自分の見方で、欠片そのものは変わっていない。
作ったものが割れることで、作れるもの/作れないものが同時に存在する。人為と偶然が重なる。“作っているようで作っていない”感じが面白かった。
そして気づいたのは、焼き物の面白さはプロセスにあるということ。絵はいつやめてもいいけど、逆に終わりもない。
焼き物は形づくられ、加工され、表面処理され、高温で定着される、と時間とともに進む。工程があるから、その時々にしかできない判断がある。元に戻れない不可逆性が、次の一歩を生む。
何でもできる状態からは、何も生まれない。制約があるから判断が生まれる。それが造形のきっかけになるんです。
陶庫──
益子で活動した合田好道さんが言っていましたが、濱田庄司さんはあれだけ焼き物を知っている人だから、益子で採れない素材で焼き物を作れば絶品のものができたはず。だけど、濱田さんは益子の素材にこだわった。それは制約を逆に捉えたからできたことだと思います。
井上さん──
まさにそう。制約を制約と見ず、それを関係として生かすのが表現なんです。
知らないからこそ、未知に触れられる。
井上さん──
知識を得るほど“禁則”が増えます。これをやったら「割れる」「焼けない」と考えて手が止まる。でも、知らない人はやってみる。知らないから無茶ができて、そこから新しい発見が生まれる。
知っていると無茶をしない。知らないからこそ、未知に触れられる。
それから「技法」と「技術」は違うと思います。技法はゴールが決まっていて模倣できるけれど、技術は身体感覚と経験の堆積だから人それぞれで、教わるというより育つものです。
作り続けていると“スタイル”ができる。でもスタイルを守るだけでは表現が止まる。表現はその都度関係を作り直す行為だから、更新し続ける必要があるんです。
素材との関係
陶庫──
今回の展覧会のテーマにも重なりますが、90年代には「素材か表現か」という議論もありましたね。流通が発展して、他の産地の素材を使うことが容易になり、益子で作陶していても「自分の表現には信楽の土が合っている」と考える作家が増えた時期でもあります。
井上さん──
たとえばいわゆる現代美術の人にとって素材は自由選択になります。FRPで作れば合理的、という選び方もある。でもそれだと、モチーフつまりは、モチベーションが素材と関係を結ばない場合がある。
焼き物を続ける人、石や鉄を続ける人、その人たちは素材との関係にモチベーションがあるから素材を任意に選択しない。素材は手段ではなく、関係そのものなんです。
壊れても作る、大きな造形へ
陶庫──
井上さんのご出身は神戸ですよね。
井上さん──
阪神淡路大震災では人が作ったものが、あんなにも簡単に壊れるのを見て打ちのめされたけれど、それでも作るしかないと思った。大きな出来事に向き合うには、自分も大きなものを作る。そこから大きな造形を作るようになったんです。
当時作った大きな茶碗の形は土を積み上げるうえで合理的。乾かし、切って分割し、焼成後ボルトで繋ぐ。乾いた土を切るのに金切りノコも使いました。素材と格闘しながら、“度を越えた形”を探っていました。
「出来事」と「感じ取ること」
井上さん──
ドローイングでも、真っ白な紙の前では何も起きない。だから、わざとワインをこぼしたりして(笑)。偶然できた染みが対象になり、そこに反応できるから次の線が引ける。
映像や写真は現実を写すから“わかりやすい”。でも焼き物や抽象表現は、「何を感じたか」「どう受け取ったか」が重なる。“わかる”より“感じ取る”。その中に、表現の深さがあると思っています。
自己表出と指示表出
井上さん──
吉本隆明さんの言葉でいえば、表現には「自己表出」と「指示表出」がある。
前者は、まだ言葉にならない「あっ」「わっ」という反応。後者は、それを他者に伝える「あそこに花が咲いているよ」という行為。
自己表出だけでは独り言で、指示表出だけでは情報。この2つが言語を構成しているといいます。
コミュニケーション能力を高めましょうっていうのは、指示表出だけを高めましょうと言っているようなものなんです。「あっ」と感じることを人とやり取りする、その感覚がまず重要。でも、それだけでは伝わらないから、表現のために指示表出性が必要になる。
両方が絡まったときに、初めて“他者と共有できる表現”になる。
夕日の話で言えば、夕日自体は作れない。けれど「夕日のように感じるもの」を作る。その“ような”を、みんなが作っている。フェイクではないけれど、フィクションです。
つまり、虚構化しないと共有はできない。表現とはその虚構の回路をつくること。どうやって自分が感じ取ったものをフィクションにするか。自分が受け取らないとフィクションにならないんです。
受け取って、もう一度外に出す
井上さん──
見たことのないものは作れない。でも、一度受け取って外に出したものは、自分の外にある対象になる。それをもう一度受け取り直して、また別の形にして外に出す。
受け取って、もう一度外に出す。その往復の中に、僕の表現があるんです。
それはつまり、自己表出と指示表出の往還そのもの。感じ取ったものを一度外に出し、それを見つめ直してまた形にする。
その反復のなかで、表現も、そして自分自身も少しずつ変わっていく。
僕は、その変化の中に“作る”という行為の意味を見ています。